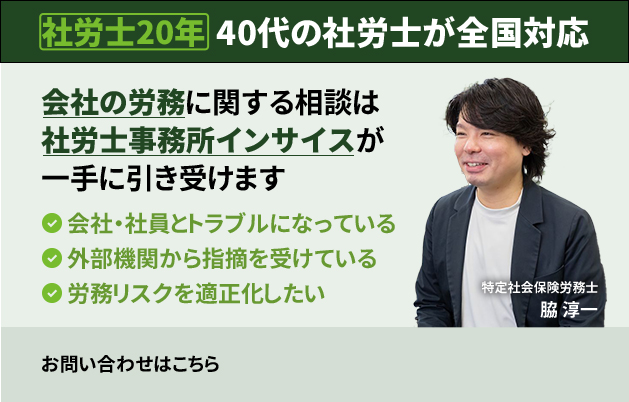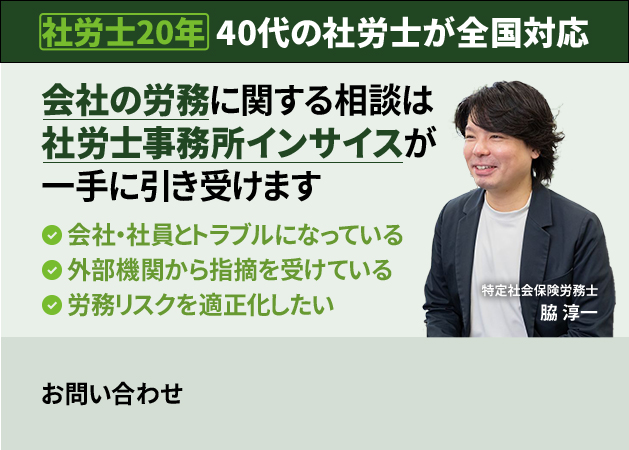教書的には指摘と改善機会の付与が重要に
![]() 能力不足って、何をもって能力不足なのか難しいです。身も蓋もないことかもしれませんが、レベルが高い仕事であればそのハードルは上がってきますし、社会人として当然できないことができず改善する気もない場合で困る場合もあります。また、「会社側の正義」だけで能力不足だと判断されていることだってあります。
能力不足って、何をもって能力不足なのか難しいです。身も蓋もないことかもしれませんが、レベルが高い仕事であればそのハードルは上がってきますし、社会人として当然できないことができず改善する気もない場合で困る場合もあります。また、「会社側の正義」だけで能力不足だと判断されていることだってあります。
いずれにしろ、もしトラブルが大きくなって裁判所ベースになった際、もっとも問われるのが「しっかり指導して改善のチャンスを与えましたか?」という点です。 能力不足の程度も重要なのですが、その人に本当に良くなってもらうために会社がどのくらい指導し、かつ改善する機会を与えていたどうか。もし裁判になると、証拠が命になるので口頭ベースではなく、書面やメモベースで見られます。
理論上は、配置転換や職種変更で改善チャンスを与えたかを見られる
もし改善指導をしっかり行った場合でも改善されない場合、仕事の適正にも問題があるかもしれません。改善機会の付与としては、そういうところも見られます。普通の採用(採用前に地位や業務を限定されるようなヘッドハント的採用でなければ)であれば、他の職種や業務内容などにチャレンジさせる機会も必要になります。
- 単に能力がないのか?
- 能力を発揮しようとする気がないのか?
- 環境適正によって能力が発揮できないのか?
- 新卒採用であれば、改善指導や職種の変更などによって、改善チャンスを与える回数は相当必要に
能力や適性は一つの職場や業務だけでは、測りにくいので他の業務を担当し、能力が発揮できる可能性を模索します。配置転換がきっかけになって、会社に馴染んでうまくやってくれれば、問題は解消して、お互いにとってベストの着地です。
ただ一方で、チャンスは与えたけれど、改善されない場合もあると思います。仮にそのような場合でも、配置転換は会社が本人の適性を測ったり、改善のための努力を行うという客観的なプロセスとなり、問題社員対応においては非常に重要になります。
このような会社が社員を改善するための努力を行っても、改善する傾向が見られない場合は、この過程が正当な解雇理由となってきますし説得力も変わってきます。また配置転換や異動をさせる場合は、本人へ『この業務や職場では適性がないと判断したから』と、その理由もしっかり書面等で伝えておくべきです。
そうしないと、単なるマンネリ解消のためだとの評価リスクもあり得ます。結果ありきではなく、本当に改善してもらうように指導してチャンスを与え、話し合いも行います。その上で改善する気がない、あるいは改善が全く見込めそうになければ、退職後の支援案を含めた別の選択肢を検討するというスタンスで対応することになります。
入社前後での能力期待値の明確化が対策に
高い目標や入社時から一定のポジションを約束して、採用することがあります。この場合、具体的な成果目標やタスクを具体的に書面に落とし、雇用契約することがポイントとなります。係争になった場合にも「事前に求める能力や成果を特定していたか?」を重要視している傾向ですので、特に採用当初から高い賃金を支払うに対しては、具体的な成果目標の合意が必須となります。
ただ、中途採用でこのように高い能力を入社時から期待していない場合でも、期待する能力や成果を具体的に設けて合意することは効果的です。「これくらいはできるはず」という認識は、思い込みかもしれません。雇用契約書等の書面で期待する能力や成果を具体的に明記し合意することで、法的効果を超えて、個別目標の共通認識がトラブル回避にも繋がります。
この具体的な目標値は、社員の業務遂行能力やスキルセットを考慮し、合理的かつ達成可能なものである必要があります。目標を設定する際には、過去の実績や同じ業務を担当している他の社員の実績を参考にすると良いでしょう。
目標設定後はフィードバックとその記録を
目標を設定するだけでなく、その達成のためのサポートやフォローアップの体制も整えることが重要です。例えば、定期的なミーティングを設けて、業務の進捗状況や遭遇している課題について共有し、解決策を模索するといった取り組みが考えられます。
能力不足を理由にした解雇を検討する際には、事前に十分な指導や改善の機会を与えているか、そしてその過程をきちんと文書化しているかが鍵となります。文書化されたデータは、事後のトラブルや訴訟の際に非常に重要な証拠となり得ます。
さらに、その指導や改善の過程で、社員の側からのフィードバックや意見もしっかりと受け入れることが求められます。それにより、社員も自分の改善のための取り組みや会社からのサポートを感じ、よりポジティブに取り組むことが期待できます。
人事考課が存在する場合の注意点
雇用契約の解消を検討する際、一つの大きな要因となるのが「人事考課」の結果です。しかし、評価者の配慮や危機感の欠如から、問題とされる社員に平均以上の評価がつけられるケースが増えています。以下、この点を踏まえた経営上のリスクと対策について解説します。
1. 人事考課と雇用契約解消の矛盾
高評価の社員に能力不足を理由に解雇を言い渡すのは矛盾しており、このギャップが企業へのトラブルリスクを増加させます。会社としては、雇用契約解消を考えている社員には、その意思が人事考課に反映されるべきです。雇用契約の解消が視野に入っている場合には、人事考課の評価は非常に影響力がある点として扱うべきです。
2. リセットリスクの存在
問題行為や指導改善の経緯が、人事考課での高評価によってリセットされる恐れがあります。その結果、解雇の正当性を示す材料が減少すると考えてください。
3. 社員の感情面でのリスク
「会社に認められている」との誤解を生む高評価の後、突如「能力不足」との理由で解雇されると、社員は深い衝撃を受けるでしょう。これが原因での対立やトラブルが生まれるリスクも高まります。
4. 経営判断の重要性
上記のリスクを考慮し、人事考課での評価と経営方針の整合性を確保することが求められます。特に能力を理由とした雇用契約の解消を検討する際には、評価結果が不利な材料となることを念頭に置く必要があります。
常に対話を
最終的に、解雇を検討する場合でも、その決定を下す前には十分な対話の機会を持つことが大切です。解雇を検討する理由や背景をしっかりと伝え、社員の側の意見や状況を理解することで、双方が納得のいく解決を追求することができます。