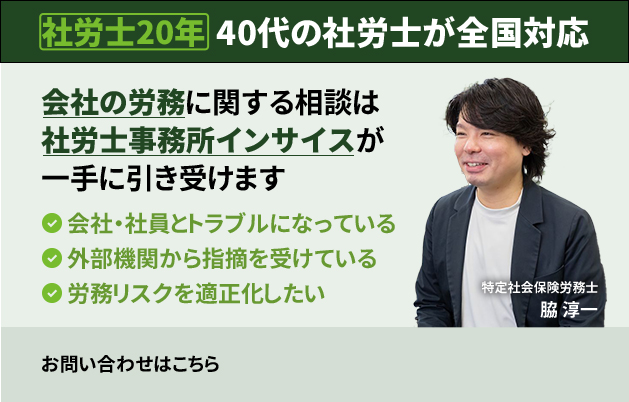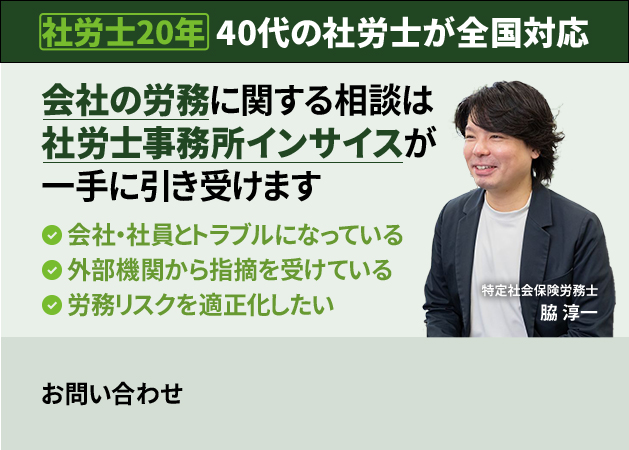労働時間の正確な把握は会社の法的責任
![]() 法令により、会社は労働時間を正確に記録する義務があります。正確な記録がなければ、法的に罰せられるリスクだけでなく、社員からの残業代請求に対して十分な反論が難しくなります。つまり、労働時間を把握しないことは、むしろ会社経営にとってリスクでしかありません。
法令により、会社は労働時間を正確に記録する義務があります。正確な記録がなければ、法的に罰せられるリスクだけでなく、社員からの残業代請求に対して十分な反論が難しくなります。つまり、労働時間を把握しないことは、むしろ会社経営にとってリスクでしかありません。
この点を鑑みると、労働時間の正確な管理は会社の法的リスク管理として絶対的に必要です。
ただ、とはいえ過剰に労働時間の集計は、人件費の増大や不要な会社内在社時間を生み出す要因となります。「過剰な未払い賃金請求」を抑止するための方法を以下で解説します。
対策1: 残業申請制度の導入
残業申請制度は、社員が残業を行う際に事前に申請し、上司がその内容をチェックして承認するというもの。これにより、無駄な残業を削減し、労働時間の把握がより正確に行えます。経営側としては、人件費の適正化や法的リスクの管理に寄与することが期待できます。
対策2: 変形労働時間制の導入
特定の業態や繁忙期、閑散期がはっきりしている企業では、変形労働時間制が有効です。この制度を導入することで、業績や労働需要に応じて労働時間を柔軟に調整できます。経営側としては、人件費の最適化や生産性の向上を目指す上で、非常に有用な手段となり得ます。
以上の対策を通じて、経営側は法的リスクを最小化し、業績の最適化や社員のモチベーション維持にも効果的に取り組むことができます。
ただし、事前に始業終業バターンを特定しておく必要があり、就業規則等に具体的なパターンを規定する必要があります。さらに、一か月単位の変形労働時間性であれば、月の開始前に各日の始業終業時刻を特定して通知すること、一年単位の変形労働時間制であれば、原則1年間を通じて個別に始業終業時刻を特定し、労使協定と共に所轄労働基準監督署への届出と労働者の周知が必要です。
また、変形労働時間制+固定残業代の場合で、シフトにおいて、法定内時間と法定外時間が明確に区分されていないと変形労働時間を否定されて、原則の1週40時間、1日8時間超が時間外労働となり得る可能性があります。これは特定がなさていないと解釈されるためです。
つまり、固定残業代の吸収時間を予め法定内の如く組み込んでいると変形自体が否定され得るという事です。
対策3: 事業場外のみなし労働時間の導入
概要
外回りの営業など、労働時間を正確に計測しにくい社員に対して、事業場外のみなし労働時間制を適用することが考えられます。この制度には、所定労働時間としてみなすものと、通常の労働時間としてみなすものの2つのタイプがあります。
例
8時間勤務の会社で、12時間外回り営業をした社員の労働時間を、所定の8時間として計算する場合、残業代は発生しません。
メリット
過度な残業の解消、人件費の最適化
デメリット
この制度は狭い適用基準を持っており、帰社後の事務作業などは原則として残業と見なされます。また、上司との同行営業は、みなし労働の対象外となることが多い。
※ 業務委託契約や請負契約について
概要
労働関係の問題を避けるために、業務委託契約や請負契約を考える企業も存在します。しかし、これらの契約は雇用契約との区別が曖昧なため、リスクが伴います。
メリット
労働基準法などの雇用に関連する法令の制限がない。社会保険や労災保険への加入が不要。
デメリット
仕事の遂行方法や時間の指示が難しく、適切な線引きがされていない場合、実質的に雇用契約と判断されるリスクが高い。このような場合、サービス残業や社会保険の問題など、多くのコストが発生する可能性がある。
業務委託契約の移行は、真に時間拘束性や細かな指揮命令がない場合でないと正しい選択とは言えず、そうでない場合にはリスクの高い対策方法であり、実態は雇用契約であることも多いです。
業務委託(あるいは請負契約)か、雇用契約かは、トラブルになった際には、最終的に裁判所が決定することなので、一般論で断定できることではありませんが、業務の時間が決まっていたり、他の社員と一緒に仕事をしていたり、会社の所有物を使って仕事をしていたりすれば、雇用契約と判断される可能性は高くなります。雇用契約と判断されれば、サービス残業の問題、社会保険や雇用保険の加入の問題が、一気に発生しますから、多大なコストを覚悟しなくてはなりません。実態にもよりますが、個別に専門家のチェックを受けてから業務委託契約、請負契約へ移行するべきです。
よくあるケースとしては、『業務委託契約していた者が、仕事中にケガをして、「実質的には労働者であるから」と、労災の申請をしようとしたところ、会社に「社員でないと申請はできない」と言われ、困り果てて合同労組(ユニオン)に相談して、労災問題だけでなく、未払い賃金の請求議論になったという事はあり得ます。