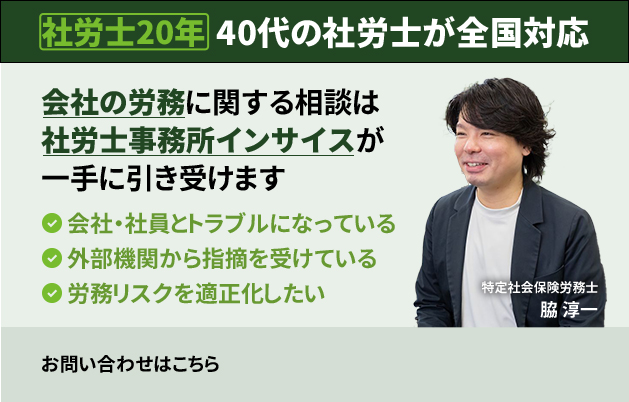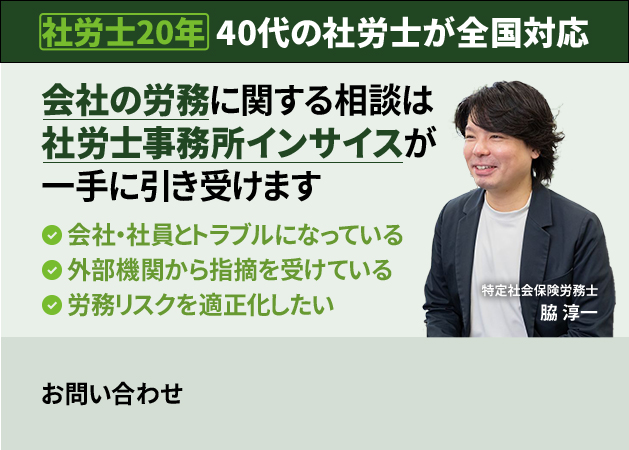諭旨退職は規定しない。
![]() 懲戒処分は、会社が社員に対して行う「制裁罰」です。社員の言動に問題があれば、懲戒処分という形で、改善を求めるものです。
懲戒処分は、会社が社員に対して行う「制裁罰」です。社員の言動に問題があれば、懲戒処分という形で、改善を求めるものです。
ただ実際には、社員に問題があったとしても、信頼関係の中で処理することがほとんどであり、口頭で注意することはあっても、何か書面にしてまで指導改善を行ったり、いちいち顛末書等を提出させることは、あまりないと思います。
しかし、例えば能力不足や、酷い協調性不足で社員を解雇等し、その後に社員とトラブルになった場合、必ずと言って良いほど「会社が指導改善しましたか?」ということを問われます。
もちろん社長や上司、管理部の方が「指導」はしています。しかし、そのほとんどが口頭注意です。
はじめは信頼関係の中で改善しようとしているわけですから、書面で注意するなんてことは、なかなかできません。ただ、トラブルになると、指導改善をおこなって改善の機会を与えたのか聞かれこれの最たるものが、「懲戒処分」になります。懲戒処分であれば、明確に改善指導のプロセスが残りますから、トラブルになった際に、内容はさておき、正当性を担保する一つになります。
したがって、やはりトラブルになった際を想定して、規定することが重要となります。他のポイントの一つとしては、「諭旨退職は規定しない」ということです。「諭旨退職」というのは、本来懲戒解雇になるよう場合で、会社が諭して、本人から退職届を提出してもらい、懲戒解雇を回避して、懲戒処分の一種として退職とするものです。
諭旨退職は本人の合意が前提になりますが、あくまで懲戒処分の一種として行うので、後に当該懲戒処分の有効性を問われるトラブルリスクが残ってしまいます。さらに、就業規則に諭旨退職の規定があると、その当時は合意退職という認識だったのに、後に「当時は、諭旨退職処分としてやむなく退職届を提出した、しかし、その処分は無効だ」と主張されることがあります。
お互いの話し合いで問題を解決することは、方向性としてはとても良いと思いますが、就業規則に「諭旨退職」の規定があるだけで、無用なリスクを抱えることになりますので削除が必要です。