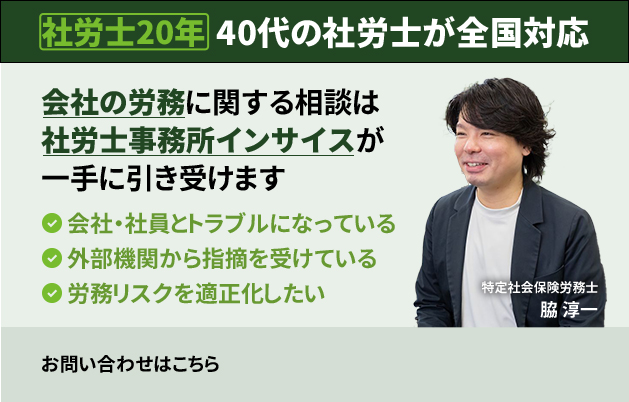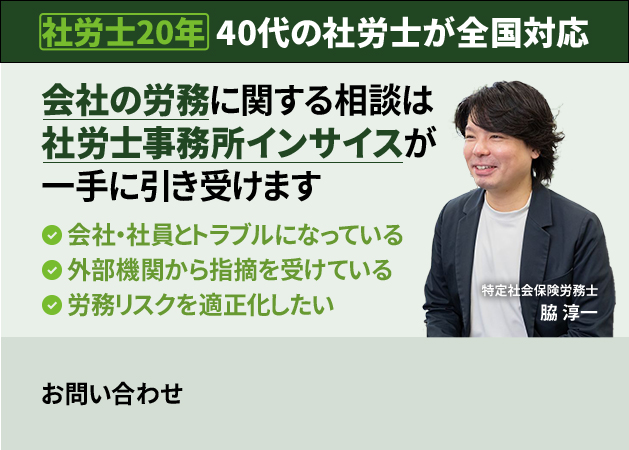36協定は必ずチェックされる。
労働基準監督署の調査においては、36協定を作成しているかどうかは、必ずチェックされる項目です。36協定を締結していない会社も未だに多く存在しますが、36協定をしっかり締結しておくことで、労働基準監督官の会社に対する印象も、随分違うのではないかと感じています。
労働基準法32条では、「使用者は労働者を1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない」と規定しています。したがって、この時間を超えて労働させると労働基準法32条違反となり、罰則は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。 実際に罰則が適用されることはあまりありませんが、いわゆる「36協定」と呼ばれる「時間外労働及び休日労働に関する協定書」を作成、締結することで、会社が残業命令をしても労働基準法32条違反にならなくなるわけです。
その36協定は、労働基準監督署への提出が必要となっており通常は1年更新です。1年を超える協定期間を締結することはできませんので毎年忘れずに締結しておきましょう。
過半数代表者の選出方法に注意!会社が指名するのはアウト。
36協定は従業員の過半数代表者と締結をすることが必要です。(過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合) そして、その過半数代表者の選出は「民主的な方法」による必要があります。民主的な方法とは、「会社が意図した社員とならないような公平な方法」ということです。
会社が「この人でいいですね?」といった信任制であったり、限られた候補者しか選べなかったりする方法は民主的な方法とは言えません。もっとも「ちょっとキミ、ここにサインしてくれ」などといって会社が指名するなんて方法はもちろんダメです。
一昔前はそこまで問題になることはなかったのですが、最近では、労働基準監督官が「社員に事情聴取させてください。」といって従業員代表者になった経緯を追及することもあります。きちっと従業員代表者と適正な締結手続きを踏んでおきましょう。
「残業時間の設定」は?
36協定には、残業時間の限度を設定する欄があります。36協定には通常、「1日」、「1ヶ月」、「1年」という期間ごとに限度時間を協定する必要があり、残業時間の上限は、1ヶ月の上限は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年間の上限は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と規定されています。
労働基準監督官は、残業時間や休日労働時間が36協定における限度時間に収まっているかどうか、必ずといっていいほどチェックを行います。協定の時間内を超えてしまっている場合は、労働基準法32条違反となりうるわけですが、現実には、このようなケースは往々にして考えられ、このような場合には、36協定に「特別条項」という条項を付記して協定を締結することで対策をとっていくことになります。
原則月45時間。特別条項でも月60時間以内が今日では妥当 。
この「特別条項」というものは、「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる。」というものであり、1ヶ月45時間の限度時間を超えて残業時間の上限を設定することが可能です。 ところが、特別条項は、従来の限度時間を超えることが一時的・突発的なものであるというような、特別の事情がある場合に限られます。例えば、業務量の急激な増加、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応等が考えられますが、年間を通じて適用されるような場合には、「特別の事情」とはなりません。
特別の事情があれば、月45時間といった残業時間の上限を超える時間を設定できるわけですが、これらの時間を超える時間設定については、労使当事者間の自主的な協議による決定に委ねられており、明確に法令等の制限はありません。ですから、例えば特別条項で「月120時間」としても法令違反とはならないわけです。
しかし、労働基準監督署の調査における本質は、しつこいくらいに繰り返し述べている通り、「長時間労働を抑制して、社員の健康を守ること」です。したがって、法令違反はなくても指導は受けることになりますし、万が一、社員が長時間労働による健康障害を引き起こした場合、限度時間が「120時間」となっていれば、裁判所などからの心象も良いはずもなく、会社は当然に責任を追及されることになります。
特別条項を設ける場合でも、年720時間以内、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。その上で実務管理では健康管理リスクから月60時間以内が理想的です。これは過労死及び過労自殺の判断基準と密接に関連する数字だからです。実務では、60時間以内であれば、労働基準監督署に36協定を提出してもすんなり受理してくれます。